 |
[[雇用全般]
[採用] [職域]
[制度] [その他]]
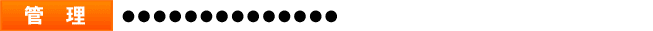

<相談事例>
脳性麻痺の社員が仕事(パソコン入力・弁当発注業務・ファスナーの穴あけ業務等)に飽きてしまい、勤務時間中にいなくなるケースが発生。どのように対応すればよいか。
<助言・提言>
会社での対応も必要であるが、登録先の就労支援センター及び保護者にも勤務状況を報告して第三者にも協力してもらうのもひとつの手であることを説明した。

<相談事例>
精神障害者1名を雇用したが、今後も2名の採用を予定している。留意点を教えて欲しい。
<助言・提言>
就労支援センターを紹介。更に、今後はトライアル雇用の活用を進める。その他精神障害者の雇用管理及び採用初期の対応の仕方等をオリエンテーションした。

<相談事例>
現在、清掃事業を行っているが、新たに製造ラインを受託することとなった。清掃と製造ラインの社員の間に賃金に格差を設けたいと考えるが、どのような配慮をすればよいか教えて欲しい。
<助言・提言>
一般企業では、年齢・勤続・経験を基に仕事のレベルアップを図り、賃金アップの体系を組むことが多いが、障害者の場合は、障害の重度化による能力低下も考えられるので、障害者の能力に見合った賃金体系をつくる必要がある。当面は職種手当として製造ラインの社員に加算するのが望ましい。

<相談事例>
内部障害者・下肢障害者・精神障害者(てんかん)の社員を雇用しているが、それぞれの障害特性を教えて欲しい。
<助言・提言>
内部障害者は勤務時間、下肢障害者には設備面での配慮が必要なこと、てんかんの社員には、服薬の確認と発症した場合の対応の仕方をそれぞれ説明した。

<相談事例>
経営的に自動車業界の厳しい状況を反映して、コスト削減を求められているため、障害者では技術者の採用を考えたい。また手帳を持たない「てんかん」の社員がいる。
<助言・提言>
障害者の現状、障害者の適職・職域の把握、各種社会資源を説明。「てんかん」の社員については、厚生労働省のガイドラインがあること及び手帳取得のメリットについて本人用に説明を準備することとした。

<相談事例>
食料品の物流センター内に知的障害者を15名雇用し、発泡スチロール箱の洗浄を行っているが、障害者を管理する体制に不安がある。アドバイスをお願いしたい。
<助言・提言>
障害者15名に対し、2名の職員で管理しており、今後も知的障害者の雇用を拡大していく意志があるため、指導員の確保と合わせて、1部門として組織的に確立したほうが良いとのアドバイスを行った。

<相談事例>
雇用率がかなり低いため、本社以外の工場で知的障害者4名と身体障害者5名を新規に採用した。アドバイスがあればお願いしたい。
<助言・提言>
採用された障害者は全て就労支援センターの登録者であったため、まず就労支援センターとの連動・連携をよく図っていくことを要請した。継続雇用をしていくためには、本人は勿論、本人の家族とも定期的な意見交換を行い、コミュニケーションを図っていくことも大事と伝えた。また“障害者職業生活相談員講習会”を受講し、資格取得をしておくことも説明した。

<相談事例>
現在採用している軽度の知的障害者のこだわり行動が多くなり、会社の業務遂行に影響が出ている。何とか対策を講じたいと思っているが、どうすればよいかアドバイスが欲しい。
<助言・提言>
仕事柄ジョブコーチでの対応では無理と判断し、社内での対策での解決を提案した。行動上、移動時でのこだわりが強いため、仕事の進め方の手本・見本をみせ、現在のやり方を新たに研修するとともに、練習を家庭で行う等の家庭協力を得ることを提案した。

<相談事例>
トライアル雇用実施後、本採用とした社員が被害妄想的に受け止める傾向にあり、対応に困っている。来てもらってどのように対応すればよいか教えて欲しい。
<助言・提言>
当センターのアドバイザーが訪問し、担当者から話を伺うとともに本人とも話をし合った結果、埼玉職業センターのカウンセラーの専門的アドバイスを貰うことを趣旨として、今後は、職業センターと連携して対応することとした。

▲トップへ戻る
|
 |
 |
| Copyright - sunrise..,2008 All Rights Reserved |
|
|
|